不動産を売却した場合、多くの場合で確定申告が必要になります。特に、初めて確定申告をする場合、「何を準備すればいいのか」「どのように手続きすればいいのか」と不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、不動産を売却した60代夫婦が、確定申告をスムーズに行うためのポイントをわかりやすく解説します。
1. なぜ不動産売却後に確定申告が必要なのか?
不動産を売却すると、その売却によって得た利益(譲渡所得)に対して税金がかかる場合があります。そのため、確定申告をして、納税または控除の適用を受ける必要があるのです。
✅ 申告が必要なケース
✔ 売却で利益(譲渡所得)が出た場合(税金が発生する)
✔ 売却で損失が出たが、他の所得と相殺したい場合
✔ 3,000万円の特別控除を適用したい場合(マイホームを売却した場合)
❌ 申告が不要なケース
✔ 譲渡所得がゼロまたはマイナスで、他の所得との相殺をしない場合
しかし、売却益が出ていなくても、税制上の控除を受けるために申告した方が有利な場合もあります。
2. まずは「譲渡所得」を計算しよう
確定申告をするには、まず不動産の売却による利益(譲渡所得)を計算する必要があります。
✅ 計算式
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 実際に不動産を売った価格 |
| 取得費 | 購入価格 + 購入時の諸費用(登記費用・仲介手数料など) |
| 譲渡費用 | 売却時にかかった費用(仲介手数料・測量費・解体費など) |
✅ 例:譲渡所得の計算
- 20年前に3,000万円で購入した家を5,000万円で売却
- 購入時の仲介手数料・登記費用などが200万円
- 売却時の仲介手数料が150万円
譲渡所得 = 5,000万円 -(3,000万円 + 200万円 + 150万円)= 1,650万円
この譲渡所得に対して税金がかかります。
3. 不動産売却時の税金(譲渡所得税)の計算方法
譲渡所得には「譲渡所得税(所得税+住民税)」がかかります。税率は、所有期間によって異なるので注意しましょう。
✅ 税率(2025年時点)
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% | 39% |
| 5年以上(長期譲渡所得) | 15% | 5% | 20% |
💡 60代夫婦が長く住んでいた家を売却する場合、多くは「長期譲渡所得(税率20%)」が適用されるケースが多いです。
✅ 税金の計算例
譲渡所得 = 1,650万円(前述の例)
課税額 = 1,650万円 × 20% = 330万円(所得税+住民税)
しかし、マイホーム(居住用財産)を売却した場合、特別控除を使うことで税金がゼロになる可能性もあります。
4. 【重要】3,000万円の特別控除を活用しよう
マイホームを売却した場合、最大3,000万円の特別控除を受けることができます。
✅ 条件
✔ 自分が住んでいた家を売却すること
✔ 親族や同族会社に売った場合は適用外
✔ 売却した年の前年・前々年に同じ控除を受けていないこと
✅ 控除を適用した場合の計算例
- 譲渡所得:1,650万円
- 3,000万円の控除を適用すると…
1,650万円 - 3,000万円 = 0円(課税対象なし!)
この場合、税金は発生しませんが、確定申告をしないと控除を受けられないため、必ず申告が必要です。
5. 確定申告の手順
✅ ① 必要書類を準備する
✔ 不動産売買契約書(売却時・購入時)
✔ 売却時の仲介手数料の領収書
✔ 登記簿謄本
✔ 固定資産税の納税通知書
✔ 確定申告書B・申告書第三表(分離課税用)
💡 3,000万円の特別控除を受ける場合は、申告書の「居住用財産の譲渡特例」欄に記入!
✅ ② 確定申告の方法
確定申告は 「税務署に直接提出」 または 「e-Tax(電子申告)」 で行えます。
- 税務署で申告する場合
- 最寄りの税務署に行き、窓口で相談しながら提出可能。
- 受付期間は 2025年3月15日まで(期限厳守!)
- e-Tax(オンライン申告)を利用する場合
- マイナンバーカードとICカードリーダーが必要。
- パソコンやスマホで申告可能。(国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用)
6. まとめ:早めの準備でスムーズに確定申告しよう!
不動産を売却した60代夫婦にとって、初めての確定申告は不安が多いかもしれませんが、流れを理解すればスムーズに申告できます!
✅ 譲渡所得の計算をする(売却価格-取得費-譲渡費用)
✅ 所有期間に応じた税率を確認する(5年超なら20%)
✅ 3,000万円の特別控除を適用すれば、税金がゼロになる可能性あり!
✅ 必要書類を準備し、税務署またはe-Taxで申告する
わからないことがあれば、税務署や税理士に相談するのもおすすめです。早めに準備を進め、安心して確定申告を終えましょう!




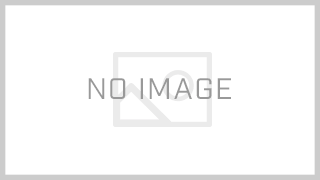

 2018年より雑記ブログ「はぴ☆らき」を開設した元銀行員夫婦。
2018年より雑記ブログ「はぴ☆らき」を開設した元銀行員夫婦。